微調色の必要性
今回は微調色の必要性とやり方について記載していきます。
そもそも何故、微調色が必要なのでしょうか?データ調色
だけでは不足なの?等、疑問に思われると思います。
結論を言えば、データ調色で色が合致する場合と、合致しない
場合があります。理由は様々なのでここでは割愛しますが、
データ調色で色が合致しなかった場合は微調色が必要になります。
データ調色の結果、実車と調色した色が違えば、不足原色を追加し、
再度棒塗り→乾燥→調色を行います。(この工程を微調色と呼称)
不足原色の選定
微調色に際して、経験がある場合は大体どの原色が不足しているか
ある程度の予測をつけることが可能です。が、経験が不足している
場合は、下記の方法で微調色を行ってください。
<注意点>
塗料のメーカーや種類によって、原色の特性は異なります。
例えば日本ペイントのレアルを普段お使いの職人さんが、
ロックペイントのプロタッチの調色を行うことは、新しい
種類の塗料を使うこととなり、原色の特性の理解が追加で
必要になります。
塗料の種類を変更して、原色の特性が分からなくなった場合も
以下の要領で微調色を行ってください。
<1>工程1 小分け
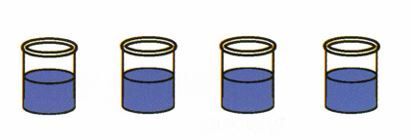
計量調色をした塗料の中から、使用した原色の数だけ各10cc程度小分けする。
<2>工程2 各原色の追加

各原色を、配合割合の20%を各容器に入れて、よく撹拌する。
<3>工程3 塗装と比較
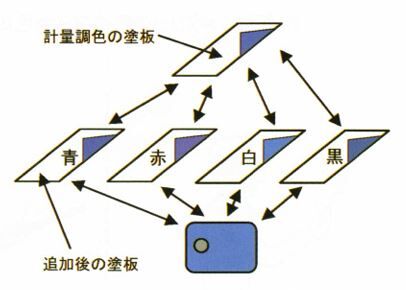
各々を塗板に塗装し、乾燥後に比色する。
・実車に一番近づいた原色を選ぶ
・計量調色した塗板と、それぞれ追加した塗板を比較して、
各原色の色足を覚える。
→原色の色足を覚えることにより、次回からの微調色が早くなります。
おすすめの関連商品
ちなみに調色に関する書籍が出ていますのでご紹介。
調色に使用する板というかフィルムはこちら
以上になります。



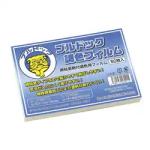


コメント